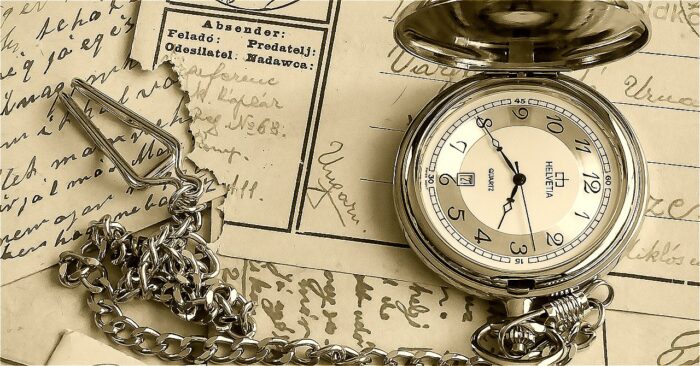島崎藤村「ある女の生涯」
「ある女の生涯」は北村薫と宮部みゆき編「名短篇、さらにあり」の最後に掲載されている。タイトルのとおり、ある女の生涯が描かれている。1921年の作品だから大正時代の終わり頃。古い時代の話と思っていたらとんでもなかった。北村薫は解説対談で「人間の狂気の描き方が近代的というか現代的」と述べており、宮部みゆきは「気が滅入る」と語っているほど、今生きる筆者にも、何とも言えず身につまされる話なのだ。
苦労ばかりだった女は年老いて、周囲に自分は正気だと訴える。しかし兄弟や親類たちには分ってもらえない。その苛立ちから感情のコントロールが効かなくなることが度々起こる。正気と狂気が入り混じり、やがて幻覚と現実の区別があいまいになっていくさまがすさまじく物悲しい。とうとうだまし討ちのようにしてもっとも嫌っていた精神病院に入れられ、看取られることなく最期を迎える。
スポンサーリンク
浦島太郎的孤独感
自分も老いと向き合わねばならなくなってきて、その哀しみみたいなものをうっすら知るようになった。
あたりまえのようにできていたことがおぼつかなくなるショックとか、老後資金が尽きる心配をする人に共感を覚える。時代が目まぐるしく変わり、知っている方法がまったく通用しなくなる心細さ。だまされてるかもしれないと頻繁にわいてくる醜い猜疑心。ろくでもない感情に翻弄されることがある。
年をとると、もっと穏やかで静かな心持ちになれるのかと思っていたのに、どうやらそんなことはなさそうだ。人間臭さはなくならないらしい。どんなに楽観的に前向きになろうと努めても、たぶん老いの寂しさが消えることはないのだ。それは浦島太郎の気持ちに近いかもしれない。
死ぬときはひとり
老いは死を身近にする。そろそろ終わりが近いと知らせてくる。この世からいなくなるというのは、いったいどうなってしまうことなのか。まったくわからないからおそろしい。
そして完全にひとりのときに、それは必ず来るのだ。だれもいっしょにいてくれない。だからわけもなく寂しくなるのか。
筆者はこうした哀しい気分を受け入れようと思う。
嫌なことは考えないほうがいいという人もいるけれど、気がかりなことほどついつい考えてしまうものである。だからこの際、無視しないでぼんやりでも考えるようにしようと思う。わからないことも答えが出ないことも。思い詰めるとからだに悪いかもしれないが、筆者はそのうちかならず飽きて、いつの間にか別のことを考えている。無理やり気分転換するよりも、自分にはこのやり方が合っている。
おとなになると、若くないというだけで、憂うつになることがあるのだ。
合わせて読みたい関連記事
スポンサーリンク
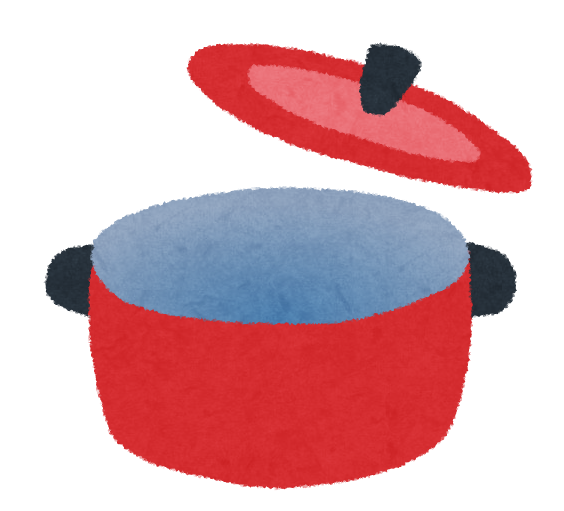 KajiBlog
KajiBlog