コネというとどんなイメージを持っているだろうか? コネクションのコネの話。
筆者はまず就職を思い浮かべる。筆者が大学生の頃は、とくに四大卒女子の就職の多くは縁故採用、つまりコネ採用だった。次々コネで有名企業の就職を決めていく友人たちを横目に、コネなし筆者は何とも惨めだったことを覚えている。実際には実力で道を切り開く者もいたので、コネなしを呪ってる時点で駄目だったなあ、と今ならわかる。
そういう筆者もコネというか、人づてでピアノの先生を紹介してもらったことがあった。受験するには志望校ゆかりの先生につくのが常識だったからだ。たまたま父が同じ系列の大学出身者だったので、先輩をたどってとりなしてくれる人物を探しあてたという。どちらかというと人づきあいがうまくないあの父が、ずいぶんがんばってくれたものだと思う。
コネは誰にでもある
コネは自分に有利なはたらきをもたらしてくれるつながりのこと。筆者はひとりでいるのが苦にならないし、どちらかというと好きである。ひとりでできることならひとりでしたいほうだ。しかし、人間ひとりでは生きられない。ひとりでできることには限界がある。
つくづくそう実感したのは子育て時代。子どもは別人格だからまったく自分の思うようにはいかない。その割に自分の影響をまともに受けて大きくなっていくのを見るとコワくなることがあった。それでもなかなか「助けて。」とは言いづらい。たまたま不登校になって、とうとう手に負えなくなって、芋ずる式にいろんな人に助けてもらうようになった。
だれともつながらない人はまずいない。ただひとりでいたいときもある。コワくて動けないときもある。今は信じられないというときもある。
それでも筆者のように、つながるチャンスはある。どんな人もひとりで生きてるわけではないからだ。
スポンサーリンク
敵をつくらない
自分にとって役に立たないつながりは不要か。
そうとは限らない。確かに切ったほうが安全なつながりもないではない。ただ「何もしてくれなかった」「冷たくされた」という理由であえてわざわざ切ることはない。「感じ悪いなあ」と思ったら距離をとればすむ。
何となく合わないとか好きになれない、さらには相手が間違っているといって、いちいち対立するのは損である。たまたま虫の居所が悪かっただけかもしれないし、実際嫌われている可能性もある。そんなときはそっとその場を離れるのが無難。
野々村友紀子氏はすばらしいことを述べている。
『買ったらダメ。勝ったらダメ。』は夫婦喧嘩に限らない。夫婦のように近い間柄でさえ受け流すテクニックが有効であるなら、人づきあい全般に使えるはず。「言い負かさないと気がすまない」「馬鹿にされたら黙っていられない」とその場の優位にばかり執着すると、コネどころか敵を増やしかねない。
そもそも社交性に乏しく希薄な人づきあいの筆者にとって、どんなつながりも貴重。時間と距離を味方にすれば、どんなコネに化けぬとも限らない。
六次の隔たり
六次の隔たりというのは、6人以内の知り合いを通じれば、どんな人ともつながれるという有名な仮説。筆者もまんざら嘘ではない気がしている。ニューヨークの道端でパフォーマンスをする日本人は、何人もの人に声をかけられ、紹介状をもらうのを見たことがある。カジュアルなコネ文化のひとつと見た。
日本では医師間の紹介状文化が盛んである。大きな総合病院にかかる場合は紹介状がないと料金が高くなるのはよく知られている。人気の医師には紹介状がなければかかれないことも少なくない。また医師が書く診断書は、障害認定や保険金の査定にかかわる一種の紹介状みたいなものである。医師と患者のつながり次第で中身が変わってもふしぎではない。
こういうことを考えていると、いつも「情けは人の為ならず」ということわざを思い出す。情けならうれしいけれど、たぶんいいことも悪いことも、まわりまわって自分に返って来る。
それほど人は、どうしようもなくつながってるってことなのかもしれない。
合わせて読みたい関連記事
スポンサーリンク
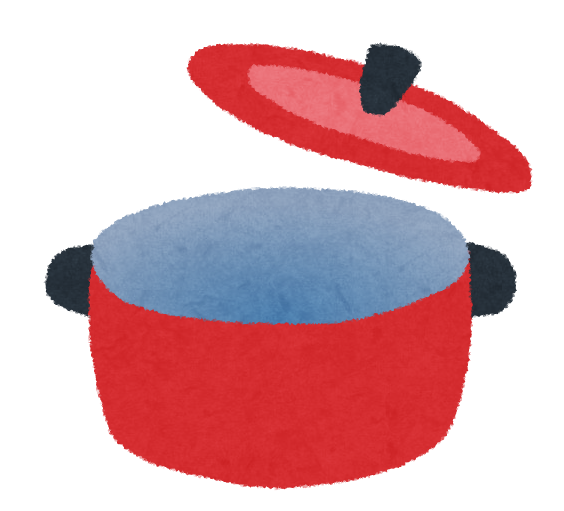 KajiBlog
KajiBlog 







