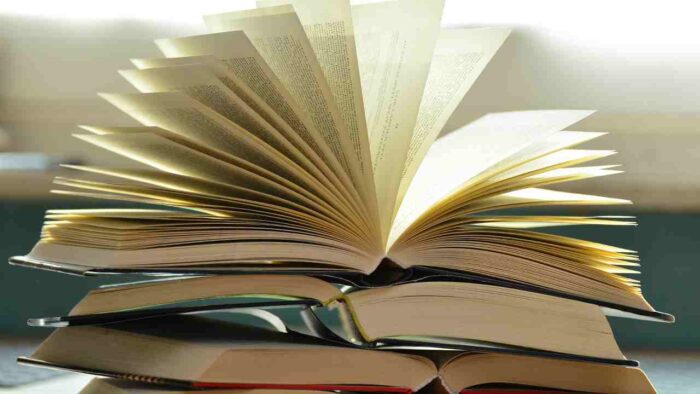本の価値は新しさではない
「古臭い本を読んでも仕方ない」と思っていたこともあった。とくに社会や経済をあつかうものは刻一刻と状況が変わる中、もてはやされるものもころころ変化している。目まぐるしくて不安になるから知りたくなって佐藤優氏や池上彰氏の新刊を追いかけてもきりがない。ついこの間まで話題になってた本がいつの間にか消えてることも珍しくない。
そんなとき、一定の評価を得ている名作を読む方がいいかも、ということにふと気づいたのだった。
新しい情報はネットでうんざりするほど流れている。見てると案外似たようなものがもてはやされているし、真偽も定かでない。そのほとんどが販売目的の広告なんだから仕方ない。
わたしも古い人間になったせいか、昔を振り返ってみるのも案外面白いのではないかと思うようになった。
一定の評価を得るには時間がかかる。時間をかけて評価されてきた作品にはきっと時代を超える何かがあるのだ。ときどき忘れ去られていた古い本が何かのきっかけで注目されて見直されるのがよくわかる。
読書に新しさを求めるのは基本的にはお門違いなのだ。
スポンサーリンク
100年たったらことばは変わる
新潮文庫の『日本文学100年の名作』は1914年の大正時代から始まる。

これくらいの小説はまだ何とか読めるが、江戸時代や平安時代の作品ともなると気軽には読めない。背景や感覚もまるでわからなくなる。
言葉というのは思っている以上のスピードで変わってしまうもののようだ。今はどうにか読めている夏目漱石や横溝正史もいずれは『源氏物語』化してしまうのだろうか。
今苦労なく読むことができることばの本は、今を生きるわたしたちにとって貴重なものなのかもしれない。
古臭いところと普遍性と
『東西ミステリーベスト100』の国内ランキング一位は横溝正史の『獄門島』である。
これは1949年昭和24年に発表された戦後間もない頃の空気がよく表れた作品だ。非常に閉鎖的な地域特有の人間模様は、現代では理解しがたいように思う反面、いまなお根深い家族という閉鎖的なコミュニティについて考えさせられる。
横溝正史の作品は昭和世代にとってはテレビドラマのほうがなじみ深いが、横溝正史は、個人的にすばらしく表現豊かな文章のうまい人だと思う。
あらためて読んでみて、古さをまったく感じさせないことに驚いたのが宮部みゆきの『火車』。
これは1986年『東西ミステリー』の旧版では選出されていなかったのだが、改訂版でいきなり五位にランクインした1992年の作品。
バブル期の強烈な地上げやカード破産、戸籍のなりすましといった社会問題の様相や背景は今とは異なるものの、やはり貧困に追い込まれ、闇社会に落ちてゆく人の姿は、現代にも通じるコワさ哀しみを想起させる名作。
ヒロインがなかなか姿をあらわさない書き方も当時は斬新だった。宮部みゆきの文章もすばらしい。
時代や環境がどんなに変化しようとも、そこに生きようとする人間の営みはさほど変わっていないことをあらためて思う。
根深く刷り込まれた<家族>という価値観そのものが、まったく新しいものに生まれ変わろうともがき苦しんでいるような、そんなことを思った。
スポンサーリンク
 KajiBlog
KajiBlog